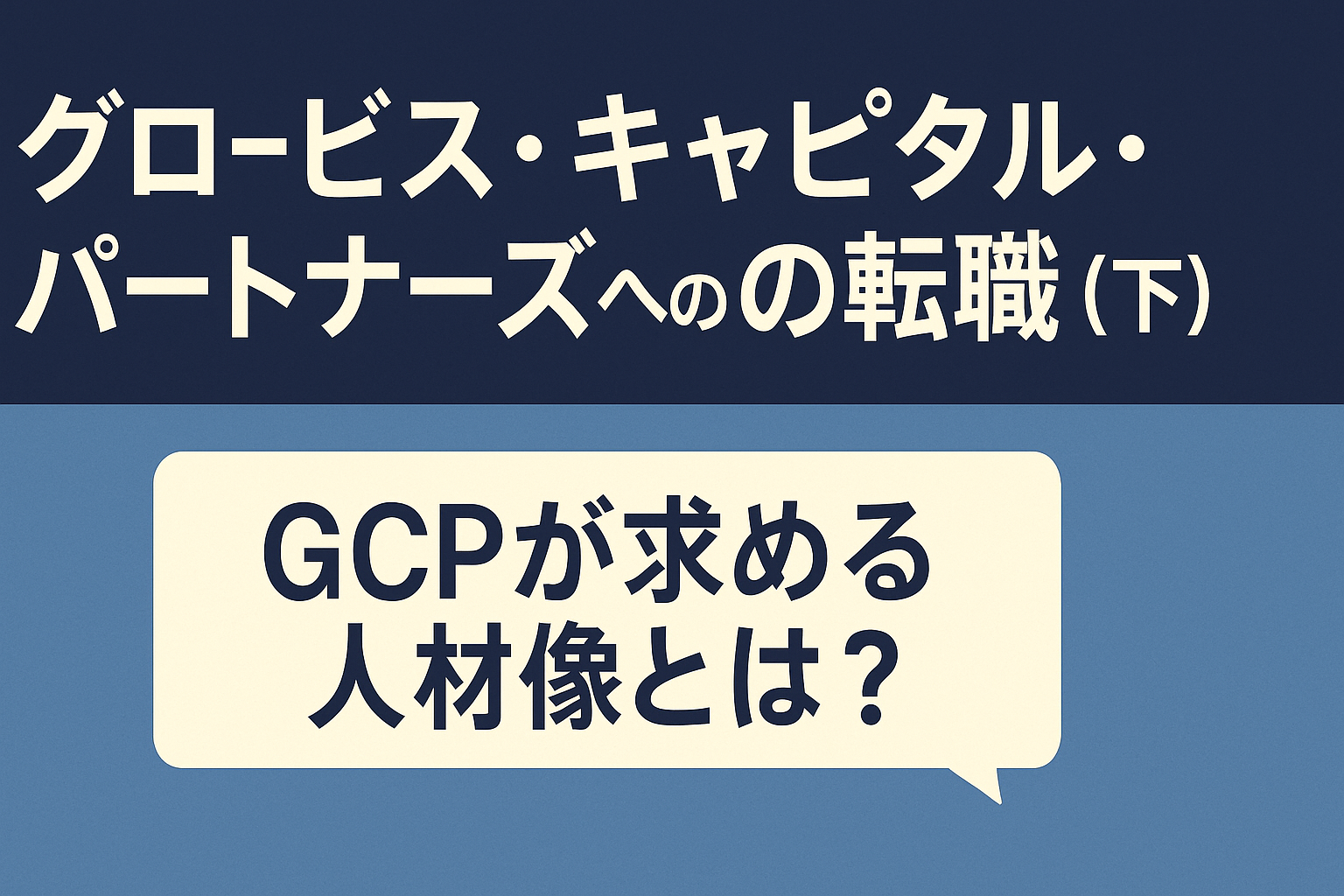
グロービス・キャピタル・パートナーズ(“GCP”)は業務拡大に伴い、随時積極的に採用活動を行っている。スタートアップへの関心が強く、日本発ベンチャーのバリューアップを経営戦略・事業戦略・組織戦略のフルスペクトラムで行い、海外進出支援をされたい転職志望者の方は、是非応募をご検討いただきたい。以下では、代表パートナーの高宮慎一氏に、グロービス・キャピタル・パートナーズの採用方針について伺った。(応募希望の方はinfo@strong-career.com迄お願いいたします。)
VC市場とファンドサイズの成長に伴い、GCP積極採用中
Q: ここで、御社のファンドサイズ増加に伴う、グロービス・キャピタル・パートナーズの採用関連についてお伺いさせてください。2019年4月に組成された6号ファンドのサイズは400億円と、23年前の創立時5億円から実に80倍になりました。今回の400億のうち、機関投資家や海外資金は何割くらいでしょうか。
A: まずは機関投資家についてですが、日本のVCの業界にとっての悲願は、機関投資家に投資していただけるアセットクラスになるということだったんです。純粋に100億円以上のファンドサイズを持続的に継続しようとすると1声10億円といった桁で投資できる機関投資家に支えていただく必要があります。
米国などではお父さんお母さん世代の年金の資金で、子供たちの世代の新たな産業が育つといったような良いサイクルが回っています。15年前は日本のVC業界はまだまだ黎明期で、ファンドのリターン、ガバナンスなどのストラクチャーの視点からもまだまだ機関投資家レディでなかったんです。
そこで、グロービス・キャピタルでは、200億円の2号ファンドで欧米の老舗VC Apaxとジョイントベンチャーを組んでグローバルスタンダードのファンドマネジメントやストラクチャーを学びました。
最初は、海外の機関投資家の皆さんに支えられ、徐々に日本の機関投資家の皆さんにも投資いただけるようになりました。
海外の機関投資家の多くの皆さんにとって日本のVCへのはじめての投資、日本の機関投資家の多くの皆さんにとってそもそもVCへの初めて投資というケースも多く、2号から6号まで継続的に複数ファンドで投資家にリターンをお返しできたことで、今では8割、9割とほとんどが機関投資家になっています。2号のころはほとんどが海外だったのが、6号では日本の機関投資家が多くなっています。
グロービス・キャピタル・パートナーズの採用プラン
Q: GCPは国内LPからの信頼が非常に強いですもんね。では社員数は設立当時の2人から何人に増えたのでしょうか。
A: 投資プロフェッショナルは12、3人まで増えました。毎年、定常的に3から5人採用していきたいと思っています。
Q: 御社志望者のメインの年齢層を教えてください。
A: 25歳から35歳くらいまでが多いです。今のところ、新卒での採用は行ったことはありません。
Q: 最近入ってこられる若手はどんなバックグラウンドを持っており、どのような価値の引き出しでエントリーする方が多いでしょうか。御社を志望する方の励みになると思いますので、質問させていただきます。
A: こういうバックグラウンドの人を求めていますというよりは、ダイバーシティ重視で、様々なバックグランドの方を求めています。例えば、コンサル、投資銀行といった外資プロフェッショナルファーム出身者、テックカンパニー、メーカーや商社の新規事業、公認会計士、スタートアップ界隈のハブになっていたような起業家よりの人などがいます。我々自体が、多様な起業家と共感して、数多くの未来を描くためには、多様性は大事だと思っています。
Q: GCPではどんなプロセスでどのくらいの期間をかけて採用を決定しますか?
A: 僕ら自身も非常にスタートアップ的なので、スケジューリングさえうまくいけば1ヶ月もかからず決まります。もちろん興味をもっていただいている方が、仕事をしながらなどスケジュールが組めないともっと時間がかかるかもしれませんが。
Q: 入社後のキャリアパスを知りたい方向けに、御社からのエグジットとしてはどんな理由でどこに行かれる方が多いでしょうか。
A: スタートアップ側に回る、独立してVCを始める、事業会社に行くというケースが多いです。
ベンチャーキャピタリストには、何故女性が少ないのか?
Q: ところでベンチャーキャピタル業界には女性キャピタリストが少ないようですが、その理由や、女性ならではのオポチュニティがあれば教えてください。
A: 男女問わず積極採用しているものの、受け身でいると、どうしても応募比率の関係で男性が多くなってしまっているのが現状です。反省も込めて、今後は積極的に女性比率を上げていきたいですね。表面的な形式論ではなく、VCは定まっていない未来を起業家と一緒に描く仕事なので、多様性そのものが、色々な形の未来をしっかりと捉え、素晴らしい多くの起業家と共感するために、ファームとして強みになるなと思っています。
VCの業務に、女性だから向いている、男性だから向いている、という業務はないと思う一方で、女性キャピタリストが少ない理由の一つに、僕らが見逃している女性の候補者や起業家がいるのではないかという視点は持っています。また、このようなポテンシャル層を顕在化させることに、チャンスや社会的意義があると考えています。
起業家のエコシステムなどと同じなのですが、やはりロールモデルが出てきて、一定のキャリアパスのモデルみたいなのができてくると、サイクルが回りだすと思います。
このサイクルをスタートさせるためには、メンタリングのような形で熱意のある女性の背中を押して、うまく仕掛けを作って盛り上げていけたらなと思います。
ベンチャーキャピタリストへの転職は、スキルよりもマインドセットが重要
Q: グロービス・キャピタル・パートナーズへの転職後に活躍されるのは、御社が提供するど真ん中のバリューとの連携性が高い思いやスキルを持つ人だと思うのですが、理想的なキャンディデイトの特徴を具体的に教えてください。
A: まずは弊社に限定せずに、一般論でいうと、ベンチャーキャピタリストは起業家マインドを持っていることが重要です。起業家からシンパシーを感じてもらえて、人として仲良くなれるということがすごく大切だと思っています。起業家からすると、全くリスクをとらない自分の保身だけしか考えていない人と気が合うわけないじゃん、というのをイメージしてもらえればわかりやすいかと思います。
加えて、何が問題であるかを定義して、その解決に向けて実効性を伴ってドライブする仕事なので、アントレプレナーでありながら経営者目線を持っていることも必要です。
これからVCに入るということ自体が、業界の成長期をドライブするという意味ですごく起業家っぽい話です。
VCというスタートアップに参加するわけです。また社外役員という立場で投資先に入り込むという意味では、スタートアップの同じ船に乗り込んで、起業家と一緒にハード・シングスを乗り越えていくというマインドセット、気概も求められます。
戦略、マーケティング、ファイナンスといったハードスキルは、案件に入りながら、または座学でいくらでも磨く機会がありますから、心配は要りません。それよりも、マインドが重要です。
コンサルと起業の中間点がベンチャーキャピタルへの転職?
VCは実態として、起業家を通じてどう組織を動かして、思い描く未来を実現するかという仕事です。あくまで事業をやるのは起業家で、起業家が主役、VCは黒子という半歩引いた立ち位置です。
とは言え、パッシブな上場株の投資家や株主として同じ船に乗っているという意味ではコンサルよりは半歩事業に近い立場であり、「投資家目線」していてはいけないのです。
VCは「投資家」と言われますが、僕は本質はそうではないし、僕自身も投資がうまいとは思っておりません。 投資は、一定情報が流通している中で、分析し、良い銘柄を選りすぐって、目利きで良いリターンをあげるという要素が大きいです。
しかしVCは、まだ何にもないところに投資をして、一緒に汗をかいて、自分自身がその事業の一つのパラメーターになって事業を作っていきます。さらに言ってしまうと、将来のこともトレンドに受け身で従うのではなく、自分が思い描く素晴らしい未来を、起業家を支えることで実現する仕事だと思っています。そういうマインドを持っていなければならないと思います。
そういう意味では、どういう人がグロービス・キャピタルを含めたベンチャーキャピタル業界への転職にフィットするかというと、純然たるプロフェッショナルよりは事業側に今一歩踏み込みたい人、または逆に個別の事業のミクロの視点をもちながらも業界や世の中の進化の意志を持っている人、そんな人かもしれません。
グロービス・キャピタルへの転職の是非:どのようなマクロ度合いの粒度で働きたいのかを考えよう
Q: ところで、グロービス・キャピタルが採用面で最も競合するのは、どのような業界ですか?
A: いまは、圧倒的にスタートアップのCxOのポジションと競合することが多いです。
なお、スタートアップとVC、どちらに向いているかは、キャンディデイトの方が人生において何を成し遂げたいかによります。 特定の領域に対して非常に高い問題意識や思いを持っている方は、スタートアップなどでバーティカルにその領域を深掘りをするのがいいと思います。
もう少しレイヤーをあげて、産業を育成したい、日本のGDPをあげたい、日本の国際競争力を上げたいとなると、 資本のレバレッジを効かせたほうがいいので、複数の会社を通じて、つまりVCでという話が良いと思います。
似たようなアントレプレナーシップ気質を持っていても、どういうマクロ度合いの粒度を持ってやりたいかで志向性が変わります。
VCに向いているのは、一定のマクロ思考がありながら、アントレプレナーシップというミクロ思考も持つ、アンビバレントな感じの人になるかと思います。
Q: なるほど。では、方向性としては似ているが、逆方向のポテンシャルキャリアとしては、通産省官僚として日本の産業をよくして成長させたい、という感じでしょうか。
A: それはあると思います。相違点は、政府としてもしくは政策を通じてとなると、よりマクロ的な視点でフレームワークを通じて、となる一方、VCではそれが投資やバリューアップを通じて、となるので、VCは行政・官対比ではよりミクロであると思います。
グロービス・キャピタル転職者が共有するビジョンとは?
Q: グロービス・キャピタルのホームページに記載のあるベンチャーキャピタリストの皆さんの動機や、やりがいを拝見しますと、共通しているのは日本の競争力を強めたい、日本発のテクノロジー会社を世界に広めたいといったところかと思います。
御社のカルチャーとしては、というかこんな人が入ってくるとフィットが高いという意味では、特にIT分野で、日本企業の世界進出をサポートして成長を促すようなシステムを作っていきたい人というのが、GCPのビジョン的にあっていますでしょうか?
A: ITなどといったセクターの縛りはありませんが、VCはローカル性の高いビジネスであり、日本発・日本アングルなしには、僕らの強み・必然性は語れません。ローカル性というのは、実際に現場に居て、スタートアップのエコシステムのど真ん中にいて、地の利があるということです。
また、資金の出し手であるLP(リミテッドパートナー)はグローバルですから、僕たちが、海外のLPに日本の投資先を売り込むというエクイティストーリーとして、”日本のここが強いから世界に進出する”というのを語る必要があります。
僕らが乗っかっている日本自体を強く大きくしないと、僕らもきつくなります。利己的に部分最適を図るというのではなく、長期目線で、日本をどうグロースさせていくのかが重要だと思っています。
将来グロービス・キャピタル・パートナーズに転職するために、経験しておくべきこととは?
Q: 御社は現状、新卒採用は実施していないと伺いました。中途で御社を志す人向けに、アプライまでの期間に経験しておくべきこと、身につけるべきことをご教示ください。
A: 経営者が考えるべき何かしらの領域で、経営者目線で、一つ専門性を尖らせること。領域はなんでも良いと思います。MBAの科目的な切り口でいうと、ジェネラルマネジメント、ストラテジー、ファイナンス、マーケティングなどです。
日々その事業のことだけを考え続けているプロの経営者に対して、支援をしていくというある意味おこがましいことをする仕事である以上、少なくともある領域においてはその道のプロである必要があります。
ベンチャーキャピタリストとして経験を積む中で、知見の深さを増していくことはできますが、入り口で何の強みもないと、なかなか起業家に振り向いてもらえません。投資先の経営会議等や役員会の場で価値を出していかないと、なかなか信頼してもらえないのです。
さらに究極的には、経営者が悩んでいる全ての領域で壁打ち相手になることを目指すべきです。なので、ベンチャーキャピタリストとしてはエンドレスに成長余地があると思っています。
Q: ちなみに高宮さんご自身はエントリー段階でどの分野の知見をお持ちでしたか ?
A: MBA留学先の米国で、デザインファームでのインターン経験があり、コンサル時代はイノベーション戦略や新プロダクト開発戦略で経験を積んできましたから、戦略策定には自信がありました。
ものづくりも好きで、ワイヤーを引いてこのリンクをここに配置してこの色でとかのレベルまでは語れないものの、経営者目線で抽象的にプロダクトを語る、このプロダクトは本来誰をターゲットにしていて、どういう使われ方をするから、見るべきKPIはこれだよね的な話はできると思っています。
投資家としてコーポレートファイナンスが語れて、戦略が語れて、さらにそれをプロダクトまでドリルダウンできるというのは、ひとつ一つは決定的な差別化にならないかもしれませんが、掛け算をしたときに希少性の高い立ち位置になりました。
ベンチャーキャピタリストは、起業家の相似形
Q: ここで毛色の変わる質問ですが、自分に技術系のバックグラウンドがない場合、テックベンチャーの技術サイドに踏み込むにはどうしたら良いのでしょうか?
A: ある技術に詳しい研究者がその領域で起業した場合に、経営者としてふさわしいとは限りません。技術を理解するのと、それをどうビジネスに転換して経営するのかは別の話だと思っています。
投資家に求められるのは、技術を研究者レベルまで完璧に理解することではなく、技術の経営的意味合いを理解した上でビジネスに翻訳し、その文脈で経営者や社外の方と円滑にコミュニケーションができることだと思います。
ただ、例えばディープテックで、技術の専門度合いが異様に高い領域で、自分ではわからない、自分では起業家に価値を出せないと思ったら、無理をしなくてよいと思っています。
VCとしての超過リターンの源泉、いいスタートアップに僕らを選んでもらうための源泉として、VCのバリューアップのケーパビリティは大事だと思っています。例えば、弊社はバイオ創薬ベンチャーには投資をしていません。その分野に精通したメンバーがおらず、新薬の承認プロセスを加速するような支援力が弱いため、僕らがやる、起業家に選んでもらう必然性がないのです。
仮にVC側がなんのバリューアップをせずともお金を突っ込むだけで儲かる美味しい領域があるならば、他のVCも殺到し、リバースオークションとなり、皆同じようなリターンに収束してしまいます。
逆に、弊社内、もしくはVCに興味をもっていただいている方の中に、新しい領域にチャレンジしたい方がいれば、やってみなはれ精神でサポートします。そのような人財の起業家精神をエンパワーして、のびのびバットを振ってもらうことこそが、新しい未来を切り開くことに繋がると思っています。
そういう意味では、本当に、起業家の相似形なんです。ベンチャーキャピタリストもVCというスタートアップのメンバーなんです。
グロービス・キャピタルのESG投資に関して
Q: ESG投資が注目されていますが、御社においてESGやSGDsにより行動変容はありましたか?
A: エグジット先である上場株の投資家にはそのような配慮が求められているので、意識せざるを得ません。
現状、そういった要素が、未上場の段階で優勝劣敗を分けるような段階には至っていません。しかしながら後ろ側の上場株マーケットでは日本でも意識し始めたということは、未上場株にトリクルダウンしてくるのは時間の問題だと考えています。
アンテナを高く張り、僕らが主体的にマーケットを作り、そこでリターンをあげることは、今後の選択肢の一つと考えています。
社内にその分野でイニシアチブを取りたい人がいれば、ファームとして全力でサポートしていきます。
また、ESGは、企業価値向上や競争力強化の目的に対するHOWと捉えており、技術、組織戦略といった同じようなパラメーターの一つとして使いこなす必要があると思っています。僕らとしても、そのあたりの支援力も身に着けていきたいと思います。
高宮氏とって、ベンチャーキャピタリストとしての仕事は、才能あるクリエイター支援と本質的には同じ?
Q: 少しプライベートなお話をお伺いします。高宮さんは学生時代に音楽にはまっていたという記事を読みましたが、高宮さんがその分野でクリエイターになろうとは思わなかったのですか?
A: その分野の才能には全く自信がありませんでしたので、クリエーターの人たちに仲間として認められて、彼らと楽しいことをするにはどういう貢献をしたらいいかというプロデューサー的な立ち位置で行動していました。現職でも同じような立ち位置ですが、好きだし向いていると思います。
起業家がプロダクトを作り、さらに言うなればクリエイティブの最たるものであるスタートアップを生み出しているところに、ファイナンスや戦略、組織づくりなどで支援して、世の中に出して、広めていくという面では、やっぱり立ち位置は同じなんだなぁと思いますし、貢献できることにやりがいを感じます。
いかに早く旅先に到着するかではなく、旅路を楽しむことが大切
Q: 高宮さんご自身がVC業界のキャピタリストロールモデルとして評価されるようになった理由をどのようにお考えでしょうか。高宮さんは大変謙虚な方なので、言いにくいと思いますが。私を含め、高宮さんと一緒に働きたいと思わせる何かを言語化すると・・・
A: VCを仕事だと思って仕事していないのかもしれません(笑)。これまでずっと、世の中の一般的な価値軸、偏差値とか名誉、昇進とかいった基準での“成功”を追求するのではなく、自分にとって楽しいことをやってきました。
僕は76世代で、大学時代にグリーやミクシー、DeNA、サイバーエージェントなど日本の主要なテック企業、インターネットサービスが出てきた頃の空気感、カルチャーのど真ん中にいて、気が合う友達(起業家)とつるんでワイワイやったり助けていたら、友達の会社が成功し、気づいたら友達と楽しく何かを成そうとしていると、それが仕事になっていました。
好きなことをやり続けて、結果が出なくても好きなことをやれたからラッキー、結果ができたら好きなことができた上に結果もついてきてラッキー。
いかに早く旅先に到着するかを追求するのではなく、旅路を楽しんでいたら、結果的に旅先にも早く辿りつけるのではないでしょうか。
グロービス・キャピタルへの転職後に感じられる、ベンチャーキャピタリストとしての醍醐味
Q: 最後に、数あるVCの中で、御社がもっとも優れていると思われる点を教えてください。
A: 僕たちが優れているとかではなく、僕らの特徴だと思いますが、経営者の一番近くにいることだと思います。 何かハードシングスが起こったら、起業家から夜中でもまず第一に電話が来て、会いに行くという関係です。ですから、起業家は難局を乗り越える喜びを分かち合ってきた戦友のような存在です。
このように、僕たちはきっちり線を引いてしまうと投資家側ということにはなってしまうのかもしれませんが、自分がその線をぼやかして、踏み込む覚悟があればどこまでも事業に近い存在になることができます。
弊社では、投資先での行動について、会社としてかっちり固めた規定や教科書があるわけではありません。基本的に各キャピタリストに委ねられており、覚悟や芸風によっていかようにも深く踏み込むことが可能です。
ベンチャーキャピタリストとしての醍醐味を、もっとも強く感じられる環境にあると思います。
