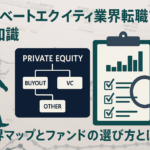
日本は、スモールキャップファンドの投資機会が多く、パフォーマンスも高い
日本では金額にして10億から20億の小型案件のパフォーマンスが比較的よく、スモールキャップファンドの雄として海外投資家からも名高いのがJ-Starです。
また一部の方は御存じですが、旧ヴァリアントのパートナーが再出発したユコンキャピタルも、有力スモールキャップファンドとして知られています。
ディールアングルの中でも、特に、中小企業のオーナー企業による事業承継案件などは、エクスクルーシブに低めのバリュエーションで投資でき、しかも企業価値を高めるために引けるレバーが沢山あります(社内規定が無かったり、経営会議が無かったり、不正が多かったり、無駄な経費や投資がたくさんあるため)。
これにより、複数のファンドが高いリターンを安定的に出し、サイズもJスターの様に100億水準から始まり、300億に成長し、昨今では750億とミッドキャップ大手並みのサイズに成長し、スモールキャップファンドからのミッドキャップへのマイグレーションが起こっています。
外資系プライベートエクイティファンドは総じて苦戦するが、カーライルとベインキャピタルは例外的に大成功
PE業界はどこの国でもローカルビジネスですので、一般的に外資系は一部を除いて苦戦します。これは企業の売り手側が外資系ファンドを警戒することもありますし、外資系ファンドが日本に進出するときはどうしても、「これまで一緒に長らく働いたことが無い人の寄せ集め」からスタートすることが多いからです。
外資系では日本のPE創世記よりカーライルなどが日本で活動し、2000年代後半にアドヴェントなど外資系有力ファンドの進出が続きましたが、結果的に日本撤退の憂き目にあったファンドも存在しました。最近では欧州大手のペルミラが、日本での方針に変更がありました。
そんな中、ディールを順調にこなし、高いリターンを挙げた海外ファンドとしては、CLSAキャピタルパートナーズも挙げられるでしょう。
比較的少ない数の企業に集中投資するスタイルですが、リターンの高さは海外投資家からも高い評価を受け、実績の豊富さとチームの一貫性(平均在職年数が長い)でも、定評があります。2024年には、日本チーム独立も果たしサンライズとして新たな一歩を踏み出しました。
外資系ファームとして長期間成功してきたのが、カーライルジャパンとベインキャピタルでした。カーライルやKKRの大手海外ファンドが日本にオフィスを構え、カーライルなどは日本特化型のファンドも設立しています。ベインキャピタルは日本での投資にブリッシュで、大阪オフィスのオープンも表明しました。
2020年初頭に設立したカーライルのファンドは、ジャパン特化型としては最大級の2000億水準となりました。なおCVCはグローバルファンドが世界最大級の4兆円規模の新ファンド設立に成功し、ヨーロッパ大手のEQTもベアリングを買収して日本進出を果たしました。
リージョナルPEファンド/グローバルPEファンドの、ラージキャップPE投資
いまやアジア最大級のPEファームに成長したMBKパートナーズも、日本で著名な案件を複数手掛けてきました。MBKのUSJ投資の大成功は、今でも多くの人が鮮明に記憶しています。創業社長のマイケル・キム氏はメディアでも、韓国一の富豪に成長したと報道されるくらい、MBKは北東アジア最大級のPEファンドとして大きく成功しました。
KKRも、進出当初は案件がなくて苦労しましたが、その後高値掴みしたと揶揄されたインテリジェンスをはじめ、結局は大成功案件をいくつか積み上げました。日本において、PEだけでなく不動産などマルチオルタナティブアセットマネジメントで着実に規模を拡大し、ブラックストーンと共に、大口機関投資家相手に日本で最も成功したグローバル・オルタナティブ・アセットマネジャーとして存在感を大きくしています。
なおUBS日本支社長であったマーク・チバ氏が立ち上げたロングリーチも日本PE業界の古株で、某国の金融機関への投資で痛い目にあったものの、日本での投資では複数のディールが高いリターンを上げました。独立系の有力ファンドから人材を引き抜くことにも成功しています。
日本のプライベートエクイティファンドは、どの程度まで大きくなれるのか
これまで日本ファンドで2000億になると、投資機会が不十分で競合とのオークションで高めのバリュエーションで投資してしまい、最後に破裂してファンドが大損、というサイクルを複数のPEファンドが経験してきました。
しかしビリオン越えのファンドレイズを果たしたPEファンドのパートナーたちは、これまでのPE市場と異なりMA市場も何倍にも大きくなり、ディール機会も増えているので、市場の成長に従いファンドも大きくならないといけないと主張します。
他方で、本来は1000億以上のファンドが集まったのに、オークション案件が大半で価格も高くなっているので、今魅力的な案件で1000億投資できる環境ではないと、大幅にカットバックして投資家からの旺盛な需要を断ったファンドも存在します。
2020年代に入ってここ数年は1000億レベル、2000億レベルのファンドレイズが相次いだ年でしたが、今回募集された大型ファンドがどこまで実績を残せるかで、日本のプライベートエクイティ市場の規模が大きく変わってくるでしょう。
自分に合ったプライベートエクイティファンドの選び方とは?
数あるPEファンドの中から、どのファンドを志望し、またアプライ戦略を立てるべきでしょうか?多くのエージェントは、求人条件を満たす人を探して面接をセットしようとするのですが、肝心なのは候補者側の個別事情にあったサポートをすることです。
①投資先の地域(ファンドの投資マンデートの地域的制約)
例えば”投資先の規模や地域”という意味で注意しておきたいのは、グローバル大企業を相手にするトップティアの戦略コンサルや投資銀行から転職してくると、前職の顧客企業に比べると投資対象企業の規模は大抵は格段に小さくなり、またドメスティックになるということです。
これは投資サイズが20億のスモールキャップや100億~200億のミッドキャップでは、企業価値は1000億以下であることが大半だからです。
そんななか、グローバルキャリア志向が強い人は、リージョナルファンドやグローバルファンド(もちろん主な担当は日本になりますが)を考えるのが良いですが、それらファンドの中でも、基本的に日本オフィスは日本のディールしか参加できないところと、グローバル案件に一緒に入れるところと、キャリア機会には違いが存在します。
②ファンドの投資戦略とのフィット
次に、投資戦略とのフィットも重要です。PEファンドの中には中小企業の事業承継が得意なところもあれば、大企業のコーポレートカーブアウトに特化したファンドもあります。ディストレスドディールの再生案件に強みを有するところもあれば、アッドオンインベストメントで市場シェアを高めていくのが得意なファンドもあります。投資先のESG対応に熱心なPEファンドもあれば、全く意に介さず、地銀と連携してリターンは低くとも地方再生系と説明がつく案件を中心に行うファンドもあります。
ご自身の個人的またキャリアでの原体験と問題意識を鑑み、どのような特色あるファンドであれば、面接で自然に正直に話されるストーリーが相手に刺さるのか、適切なアドバイスを受けることが有益です。
③LP投資家層の違い
このポイントとも関連するのが、LP投資家層の違いです。欧州の公的年金と、中東の国府ファンドと、香港のファンドオブファンズと、日本の銀行系では、LP投資家が求めるものが(もちろん共通するポイントもたくさんありますが)変わってきます。
その違いは好まれる投資戦略、求めるリターン目線、ESGなどへの社会的責任に関するスタンス、またLPが求めるサービス(時にノーフィーノーキャリーの共同投資、時にはファンドリターンよりLBOファイナンスのアロケーション提供)が違ってくるのです。またどのようなLPに支持されているファンドなのかを見ることで、プライベートエクイティ業界の中でのポジショニングも大きく変わってきます。
④自分が学びたいこと・経験したいことと、PEファンド各社のフィット
最も重要なのが、自分が経験し、学びたいことと、そのPEファームの人事戦略とのフィットです。プライベートエクイティファームの中には、投資とバリューアップとエグジットを一気通貫で経験することが本人の成長につながるという姿勢で運営しているところもあれば、案件遂行とバリューアップチームを完全に分けていて、投資のエクセキューションが主な役割というファンドもあります。
逆に、地方の投資先に取締役会のメンバーというより、経営陣として送り込まれるファンドもありますし、小規模なファンドの小規模な投資先ですが、若くして社長を任されて、経営トップの何たるかをキャリアの早い段階で経験させてくれるPEファンドも存在します。
⑤企業カルチャーとのフィット
企業カルチャーとしても、極めてフラットな社風を持つPEファンドもありますが、日本の銀行系のようなヒエラルキーカルチャー、ないし米国投資銀行やコンサルファームカルチャーで労働時間が恐ろしく長いファンドもありますし、逆に放任主義で勝手に何でもかんでもやらしてくれるPEファンドも存在します。
ストロングキャリアはこれら多くのPEファームで働く講師陣がキャリアアドバイスを提供しており、また日本の多くのPEファンドに投資家の立場で創業社長クラスとやりとりをしてきた講師が、各ファンドの違いを熟知した上で、個々人にフィットの高いPEファームの選択および選考支援を無料で提供しております。
