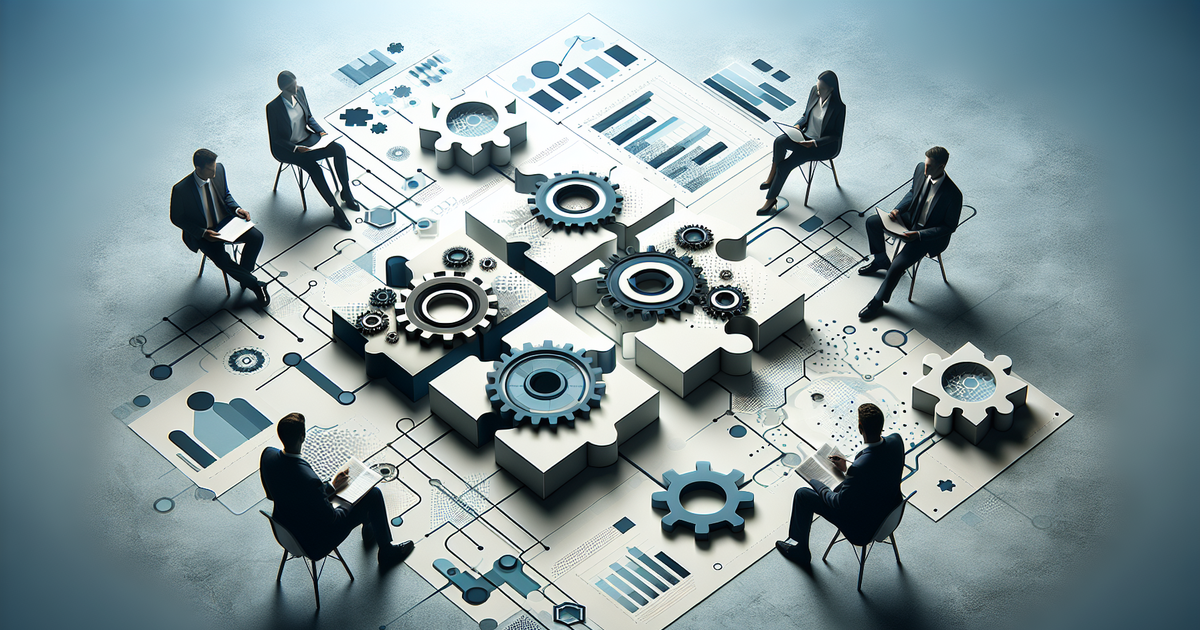
投資銀行、コンサルの就活面接で重要なのが、グループディスカッション。グループディスカッションは面接官からどのように見られているのか、またどのように立ち振る舞うのが良いのか、結局は自分の意見を押し通す人が通っているのか、という東大工学部の学生さんからの質問に答えます。端的に答えれば、ガンコな人は絶対ダメです。大切なのは要するに①他人の知を引き出し ②全体の雰囲気を協調的に盛り上げ ③意見を押し通し野ではなく、全体の視点とインプットをまとめた集合知を効果的に産み出せることを示すことが重要になります。
グループディスカッション大成功の3大パターンと、留意したい5大要素とは?
東京大学工学部 Tさんより質問
グループディスカッションでのたち振る舞いについてお伺いします。
結局自分の意見を突き通す人が通っているイメージがありますが、本当にそれでいいんでしょうか?
どんな人でも意見に矛盾点が少しは見受けられ、それを無理やり押し通す人もグループディスカッションで見受けられるような気がします。
また、志望動機についてお伺いします。一応各社ごとに志望動機を変えているのですが、一回、最終面接で志望動機の部分で落とされた気がするので、志望動機を言う上で注意すべきことを教えていただきたいです。
グループの雰囲気と生産性を高められる人材かどうか?
まず端的に応えましょう。ズバリ、”結局自分の意見を突き通す人間”は、ダメです。
個別面接でなくグループディスカッションだからこそ見れるのは、協調性やチームでどう振舞うかです。
そのグループの雰囲気を良くして生産性を高める人かどうかが大切です。(ま、中にはなーにも考えてない面接官もいるのですが)
仮にあなたが自分勝手で我が強く、相手を委縮させるタイプなら、これを機に生き方を変えないと、学生時代はまだしも、社会ではつまはじきにされ、活躍の場がどんどん失われてしまいます。
逆にそういう性格が治らない確信がある方は、下手にグループディスカッションや面接でだけ協調性をアピールするのはお勧めしません。
むしろ一人で完結する研究者、学者、発明家、小説家、ないし宗教指導者になって壺でも売るなど、グループワーク不要の生き方を真剣に検討されることをお勧めいたします。
グループディスカッション、3大要素と、賢者の5大留意点とは?
詳細に移りましょう。グループディスカッションでの好ましい立ち振る舞いに関してまず大切なのは、
”①他人の知恵を引き出して、
②良好な関係を築きながら
③よいグループウィズダム(集合知)を産み出すのに主体的貢献をしている”と思われることが大切です。
当セミナーでは総じて、
A. 議論の全体感を踏まえて、
B. 分析のフレームワークの軸出し、
C. 分析結果に整合性のある解決策の複数提案、
D.また発言できていない人を活性化させ、
E.いい議論の雰囲気を出すチームワーク感を心がけること
を推奨しています。
こんなひとが落ちる!上ずった声で緊張しながら、やたらと他人を攻撃するのが最悪のパターン
強く自分の意見を押し通した方がいいというのは、かなり正反対ではないでしょうか。仮に答えが正しくても、協調性のない振舞いは嫌われます。
うわずった声で早口でまくし立て、無礼な調子で他人の意見をさえぎったり、逆に相手の意見を尊重している素振りを見せようと必死になってるな、というパフォーマンスも、面接をする側にはひしひしと伝わってくるものなのです。
かりにそういう暴走ファイターがグループの中にいたとしても、あなたは知性を分析の軸とフレームワークの設定で示し、協調性とリーダーシップを落ち着いた感じのいい笑顔を忘れないコミニュケーションと、他者への配慮で示しましょう。
これができて一旦「いいやつ」と思われたなら、多少の矛盾や勉強不足があってもご愛嬌。結局、好かれる人が上に上がるのがビジネス社会なのです。
「最終面接、志望動機がダメで落とされた、、、」系の後悔は、ほぼ無意味
なお志望動機で最終面接落とされた、、というご懸念は、たいてい的外れです。
実際は、志望動機の一つや二つ悪かったところで、他の要素が素晴らしかったのに落ちる、ということはありません。(といっても変わった面接官も居ますので、断定はできませんが。。)
グループディスカッションに限らず、インターンでもそうですが、結局のところ、
①このひとは一人で働くのみならず、人を上手く巻き込んで、
②いい職場雰囲気とカルチャー形成に貢献しながら、
③人を上手くレバレッジして、大きな成果を出せる人かどうか”が企業にとって非常に重要であるということを心に留めておきましょう。
別に一人で物凄く賢くなくてもいいので、チームを組んでチームの成果を高められる人が、企業にとってはありがたいのですから。
