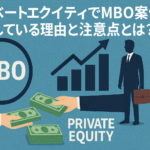
近年プライベートエクイティ業界で急増している、マネジメントバイアウト(MBO)案件。MBO急増の背景と注意点、そしてMBOが「二段階取引」になる深いワケを、端的に解説致します。
マネジメントバイアウト(MBO)→非公開化が急増する背景
近年、プライベートエクイティ案件の中でもMBOが急増しています。その理由の一つとして、上場しているメリットがもはや乏しいわりに、上場を維持するコストが高いと感じる企業が増えていることが挙げられます。
上場していると四半期決算の準備も面倒ですし、コストがかかります。英ユニリーバが四半期決算開示を廃止したことが話題を呼びましたが、その後の株価が競合他社をアウトパフォームしていることを考えると、実は四半期決算は「特に必要ないのにやっている企業が多い」ということを示唆しているとも言えます。
この四半期決算は、経営陣の判断に大きな影響を与えます。企業経営を短期志願的にし、長期的な思い切った投資を抑制する作用もあります。結果的に儲かっていない企業はますます将来のための長期投資が出来ず、3か月ごとに結果が増益になるような、既存事業の延長戦での動きが増えてしまいます。
企業及び社会のイノベーション促進を考えた時、四半期決算はその弊害も大きいものなのです。(もちろん、四半期決算の御陰で仕事がある職業も多いのですが、人類および社会全体のリソース配分として、行き過ぎている感が否めません。)
そんな中、短期的な株主の意向に左右されず自由度の高い経営をするための選択肢として、MBO(マネジメントバイアウト)が増えてきています。これは文字通り、経営陣が株式の過半数を取得して支配株主になることを意味しますが、経営陣だけで十分な資金を出資するのは至難の業です。
そこで企業経営陣はプライベートエクイティと組んでMBOを行うわけですが(もちろんストックオプションのアップサイドが大きいからでもありますが)、これは資金規模が大きくなったので投資金額も大きくなっているプライベートエクイティファーム側、また非上場化を企業に持ちかけてフィーを稼ぎたい証券会社側の思惑と結びつき、MBO案件急増の背景となっています。
「証券会社は上場させて稼ぎ、非上場させてまた稼ぐんかい」と突っ込みたくなる方もいらっしゃるかもです。
しかし上場で知名度とブランドと資金調達が必要な段階の企業と、既に知名度とブランドと社会的信用があり、資金調達ニーズもなく、オーナーが既に上場でエグジットした企業とでは、異なるニーズがあるのです。
MBOの留意点:ちゃんとしないと、経営陣は訴えられるリスクだらけ?
様々なステークホルダーの思惑が絡んで行われるMBOですが、これは「きちんとしないと大きなリスク」を孕みます。何といっても、経営陣の利益相反は避けられない事態だからです。
経営陣は株主利益を最大化するFiduciary Duty(善管注意義務)を有するので、売り手企業の株主の立場では、売却価格を吊り上げなければなりません。これに対し、買い手企業の経営陣という立場では、買収価格を極力抑えたいものです。
自分が売り手と買い手両方の経営陣であり、両方の株主にも責任があるとしたら、このコンフリクトはどのように解消されるのでしょうか?
MBOにおける経営陣の構造的な利益相反を防ぐメカニズムとは?
このようにMBOにおける取締役は、高く売る必要と安く買いたいという構造的利益相反を有しています。おまけに一般株主より情報の非対称性があるため、利益相反性がより高まります。
下手をすれば善管注意義務違反で、売り手の少数株主から損害賠償請求を求められるリスクもあるのです。
そこで独立した第三者委員会の設置や、第三者算定機関からの株式算定書の取得が必要とされてきました。しかし、実態はと言えば「適当な算定値段になっている」ことへの批判が大きくなっていました。
また公開買い付け日を通常より長い30日に伸ばすことになっていますが、何かと意思決定に時間がかかるカルチャーを鑑みますと、日本ですとたかだか30日くらいでは動く対抗者はあまりいません。
一応少数株主の意向を保護するために、MoM(Majority of Minority)という、少数株主の過半数が公開買い付けに応じる必要があるというプラクティスが存在するのですが、これは使われないことが多かったものです。
2019年に導入された、新たな「第三者委員会」の指針
上記のようないささか形骸化した「利益相反防止メカニズム」を改正すべく、2019年に新しいMBO取引の指針が出されました。
そこでは、このMoMをつけるべきかどうか、フェアネスオピニオン(取引価格の公正さに関する第三者の意見)が必要か不要か、算定書をこの機関に頼んでもいいかなどの判断を行う、ゲートキーパーとしての役割を担う第三者特別委員会の責任を重くしたのです。
その特別委員会の構成要因は社外取締役と社外監査役(ビジネスをわかっているうえ、株主に対して義務を負っている)から基本的に選ばれます。
つまるところ、これまで適当な存在であった「第三者委員会(往々にして、第一人者の陰の友人が多かった)」の責任が明確化されたのです。下手したら訴えられるのは彼らという位置づけになったので、真剣度も当然上がることになります。
少数株主に要注意:マイノリティ・スクィーズアウトの注意点
なお少数株主保護メカニズムに関しても、注意しなければなりません。マイノリティ・スクィーズアウトとは、MBOなどの時に、「売りたくない株主」に強制的に株を売らせるメカニズムです。
「株を売りたくない人に、無理矢理株を売らせることなんてできるんか?」と驚かれるかと思いますが、実はできるのです。株式等売り渡し請求というのが会社法であり、対象株式の総株主の議決権の9割以上を保有していると、これが可能になります。
スクィーズアウトのやり方はいくつかあるのですが、よくあるのが株式併合です。例えば2株を1株にすると、100株は50株になります。このような株式併合で一般株主が持っているのを1株以下にして端数株にするのです。
会社法の制度では、1株以下は株扱いされません。よって株式併合の決議さえ出来れば、スクィーズアウトを実現できることになります。 (ただし、株式併合を行うには、三分の二の株主の同意が必要。)つまるところ、ほぼ全てのMBOは二段階取引になることが御理解いただけたことでしょう。
最後に要約しましょう。まず金融証券取引の規制に基づき、公開買い付けで三分の二の株式を取得します。そしてその後、二段階目の取引でマイノリティ・スクィーズアウトを行うのです。
このように、既存の会社法や関連法律のせいで生じている「できない事」の数々を可能にする法制度整備も、プライベートエクイティ業界の発達には不可欠であることが御理解いただければ幸いです。
